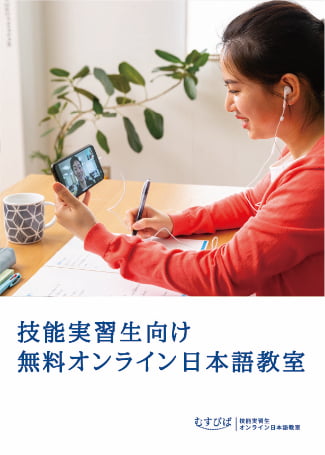ベトナム人に日本語を教える上でおすすめの方法
建設業や製造業、介護の現場等では、技能実習生や特定技能、技術・人文知識・国際業務といった在留資格で来日しているベトナム人が数多く働いています。彼らはまじめで意欲的ですが、「日本語が話せないために仕事を十分に任せられない」と感じている人事担当者や経営者の方も少なくありません。
今回は、ベトナム人にとって日本語がどのように難しいのかを言語面から解説したうえで、彼らに合った 日本語の教え方についてご紹介します。

ベトナム語と日本語の違い
ベトナム語と日本語の大きな違いとして、文法と発音が挙げられます。
日本語では、「は」「が」「を」「に」などの助詞を使って、文の中で誰が何をするのかを示します。
たとえば「私はご飯を食べます」という文では、「は」が主語、「を」が目的語を示しており、語順を入れ替えても「ご飯を私は食べます」など意味が通じる構造になっています。
一方、ベトナム語にはこのような助詞が基本的に存在しません。その代わりに「語順」で意味を伝える言語です。たとえば「Tôi ăn cơm(トイ アン コム)」は「私 ご飯 食べる」という意味で、主語→動詞→目的語という順番が固定されています。語順を変えると意味が通じなくなる場合もあるため、語順に非常に依存しています。
このような背景から、助詞の概念に慣れていないベトナム人にとって日本語の助詞を覚えて使いこなすことは大きなハードルになります。
さらに発音についても、ベトナム語には6つの声調があり、音の高低や抑揚が意味を左右します。一方で日本語は抑揚が少なく、似た音が多いため、聞き取りや発音の違いが把握しにくい傾向があります。
加えて、日本語にはあるがベトナム語には存在しない発音もあります。たとえば「つ(tsu)」の音は、ベトナム語には「ts」の音がなく、「ちゅ」や「す」に近い発音で代用されることがあります。このため、「つくえ(机)」や「つかう(使う)」といった単語が聞き取りづらかったり、正しく発音できなかったりするケースも少なくありません。
ベトナム人に日本語を教える時のポイント
日本語とベトナム語では助詞や文の構造が異なるため、単語や文法を暗記するだけでは自然な会話ができるようにはなりません。助詞の使い方や語順に慣れるには、単語単位ではなく「まとまった文章」を聞いて理解する練習が必要です。また、自分の口で繰り返し話す練習を行うことで、知識が実際の会話で使える力に変わります。
さらに、日本語の正しい発音を身につけるには、正しい発音ができる先生から学ぶことが欠かせません。技能実習生の中には、母国で日本語を学ぶ際、ベトナム人の先生が誤った発音で教えているケースがあり、そのまま真似してしまうことがあります。このような場合、一度身についた間違った発音を直すのは難しいため、学習初期から正しいモデルを示すことが重要です。
また、「現場で使える表現」を優先的に教えるのもポイントです。「これをここに置いてください」や「次にこれを使ってください」といった、指示や動作に関する表現を繰り返し教えることで、実務と結びついた学習が可能になります。
さらに、ベトナムの文化では「人と人の関係性」が重視されるため、「自分のために教えてくれている」という感覚が学習意欲につながります。日常的な挨拶や簡単な声かけを続けることが、信頼関係の構築にもつながります。
ベトナム人向け むすびばのオンライン日本語教育について
むすびばでは700人以上のベトナム人に日本語教育を提供してきました。建設や工場、介護現場で働くベトナム人が仕事で求められる日本語教育プログラムを提供しています。一般的な文法中心の学習ではなく、仕事現場に即した語彙・表現の習得を目指し、実践的な会話練習を通して、「現場で使える日本語」の定着を支援しています。
また、全ての教材にベトナム語が対応するため、ベトナム人が学びやすい体制が整っています。ベトナム人の日本語力向上は、業務効率だけでなく職場全体の信頼関係にも直結します。
むすびばでは、日本語が上達して仕事や生活がスムーズになり、1人前として働けることを目的に授業内容にしているので、短期間でも会話力が向上する内容になっています。
資料ダウンロード
プログラムの特長や、カリキュラムの内容が記載されたパンフレットを無料でダウンロードいただけます。